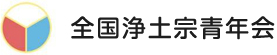生きとし生けるものとともに
お釈迦さまのご在世より、雨季には修行者たちは一カ所に集まって集団で生活をした。この集団生活を「安居(あんご)」と呼ぶが、草木が芽吹き、昆虫たちが盛んに動き出すこの時季に無用な殺生をしないようにする慣習である。この「安居」を通じて修行僧は自身の罪深さ、どんなに殺生しまいと努めても殺生せずには生きてはいけないといった罪業(ざいごう)感を深めるのである。米・ペンシルベニア州立大学のヴィクトリア・ブレイスウェイト教授らの共同研究などから、魚にも鳥類や哺乳類と同様に痛みや苦しみを感じる能力が備わっていることが証明されている。しかもその能力は、ヒトの新生児や早産児以上のものであるという。
こうした現代科学の知見は、「魚は人間ではないのだから、人間のように慈しんだところで意味がない」といった考え方を退ける。現に動物実験をはじめとして、レジャーとしての釣りなどにも倫理的観点から先進国を中心に法規制が始まっている。制度の改正には十分慎重であるべきとした上で、ブレイスウェイト教授は著書『魚は痛みを感じるか?』(高橋洋訳、紀伊國屋書店、2012年)の最後を、「未知の領域を探究する際には、知識、教育、オープンな心構えが最良の案内役になることは確かであろう」と結ぶ。
数年前、地元の漁師の男性が「アイツらな、絶対痛がっとるで」と、釣り上げた魚たちの甲板での様子をしみじみと話されたことがある。学問的成果を待たずとも、魚が痛みを感じていることを漁師は肌でよく知っているのだ。
むかし播磨国(はりまのくに・現在の兵庫県南西部)に漁師を生業(なりわい)とする老夫婦がいた。二人は魚の命を奪い続けてきた報いにより、死後は地獄に落ちるのを免れないと怯えていたのであるが、この地に法然上人が赴かれた際、上人に胸の内を明かし、涙ながらに教えを乞うた。
法然上人は、「あなたたちも極楽浄土に生まれたいと心から願って南無阿弥陀佛と称えるならば、お念佛を称える者を一人たりとも漏らさず救い取ると約束された阿弥陀さまのそのお誓いのままに、臨終の夕べには阿弥陀さまのお迎えを頂戴して必ず極楽へ往き生まれるのですよ」と懇ろに説かれたところ、二人とも今度は喜びの涙を流したという。二人は以降、昼はお念佛を称えながら魚を獲り、夜は家に帰って夜通しお念佛に励み、終には安らかな臨終を迎えたと『法然上人行状絵図』(第三十四巻第四段)に伝えられている。
お釈迦さまは、母親がわが子を命がけで守るように生きとし生けるすべての命を慈しまねばならないと説かれた。しかし、人間の営みは生きものたちの計り知れない犠牲の上に成り立つものであり、真摯に向き合えば向き合うほど、罪の自覚を強くする。
盗みせず 人殺さぬを よきにして
われ罪なしと 思うはかなさ (徳本上人)
人が身にふるまい、口に語り、心に想うところのすべての悪行を、地獄の閻魔大王はことごとく閻魔帳に書き連ねるというのだが、早々に書き切れなくなるのではないか。誰の帳簿を開いても、中は真っ黒け。人はみな老夫婦と何ら変わりのない身の上であると気づいたとき、法然上人のお言葉が心に響く。
老夫婦の深い罪の意識は、言うまでもなく二人の優しさや誠実さの裏返しに他ならない。そして、そんな彼らには「南無阿弥陀佛」をただひたすら口に称えて極楽へ往生するという救いしかなかった。
ここに人間としての最も清らかな輝きと、この上ない安らぎを見るのである。
南無阿弥陀佛
2013年07月11日
愛媛県南宇和郡 延命寺 吉田哲朗